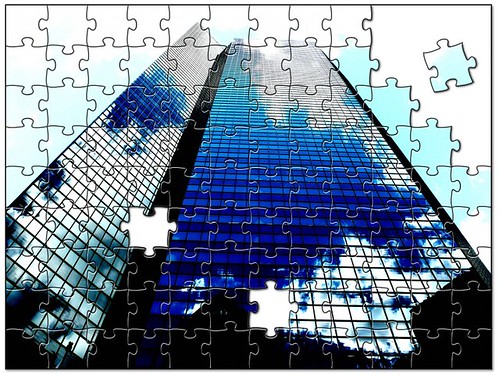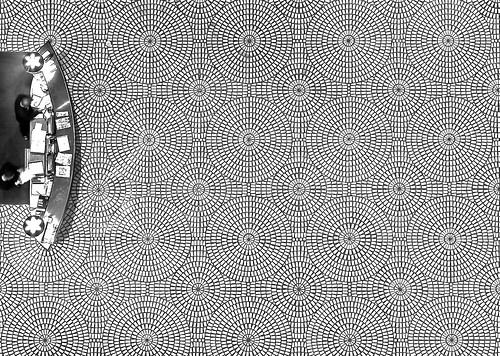アメリカの投資銀行が、リスク付債権を大量販売し、結果として金融バブルを発生させました。サブプライムローンという、銀行からも一切のローンを拒否された人々に大量の住宅資金を貸付け、借り入れ後数年でその利息を跳ね上げる時限装置を組み込み、結果、経済を破綻へと導きました。
それだけではありません。アメリカのカードローンは、完全に滞りなく支払わないと、懲罰的に利子を引き上げることが認められていました。これは禁止する法案が通ったようです。
また、アメリカの破産原因で最も多い理由は「病気治療」。民間の医療保険は、持病を隠していたと言って支払いを拒否します。既往症という名前で、保険に入る前のカゼ・インフルエンザさえ対象にし、医療保険の支払いを拒否。 これもオバマ政権の公的医療保険で廃止されるかもしれません。
こんな「欲張りの投資家とそれに加担する金融」の構図に、メスを入れるときが来たようです。
音楽産業とマスメディアの次にインターネットが破壊するのは金融業界だ–ついに
in TechCrunch Japan
・・・私は、もう一つの金融システム、銀行が生まれ変わらないかと思っています。
本誌はこの連中についてすでに書いてきたが、ついそこまで来ている革命の、大きさを知るためには、彼らを「群」として見るのがよいだろう。彼らは金 融業界のいろんな部分を攻撃しているが、共通点が一つある: 最近やっと、金融のプロたちと一般ユーザの両方が彼らに対し真剣な関心を持ち始めたことだ。以下のリストは網羅的なものではないが、私がすばらしいと感じ たサービスを挙げてみたい:
-Wongaはサラ金を変えようとしている。 貸し手から取る手数料は高いが、利用者には早期返済を奨励する。そのため、緊急時貸し付けの利息と手数料は比較的低く抑えられる。Wongaの収益は、実 際に返済が行われたときにのみ発生する。従来のクレジットカードやサラ金は(利息先取りにより)、利用者の負債期間が長ければ長いほど、その金額が大きけ れば大きいほど、儲かる仕組みだった。
-kaChingはミューチャルファンドを変えようとしている。 平均3%だった手数料を1.5%に下げ、投資ファンドマネージャたちがやってることに透明性を持たせ、彼らの過去の実績だけでなく、今何をやっているかも 公開する。それまでは、ファンドマネージャは今管理している資産の総額で報酬が決まり、パフォーマンスは無関係だった。この旧弊により、ファンドのパ フォーマンスは劣化し、投資対象の切り換えも機敏に行われなかった。kaChingは、今どんな投資が行われているかを投資家に対し透明にすることによっ て、投資家がより多くの専門家ファンドマネージャと接しられるようにし、従来の旧弊を逆転しようとしている。
-SquareとBling Nationは、 支払いの仕方を変えて、それをより便利にし、ATMやカード(Visa, Mastercard, …)の利用で取られる手数料をなるべくなくそうとする。彼らの方式は、トランザクションの関与者全員(エンドユーザ、小売り業者、銀行)にとって有利であ る。Bling NationのファウンダでCEOのWences Casaresは、“VisaやMastercardのやり方を激しく憎んでいる人がこんなにいるとは知らなかった”と言っている。
-“えっ?そんなのあり?”の筆頭がBlippyだ。このソーシャルな支払いサイトは、従来は不透明だった価格政策をオープンにし、ユーザが価額をほかの多くの人と比較できるようにする(あのホテルで友だちがいくら払ったかが分かる)。Blippyの未来はかなりTBD(to be determined, 未定)だ。人びとが過去10年で友人や位置情報を平気で共有するようになったのと同じく、今後、お金の情報も平気で共有するようになるか?…Blippy の未来は、この一点にかかっている。答えはノーかもしれないが、しかし料金や価格に透明性が実現すれば、消費者にとってはお得な事態が訪れるはずだから、 そこを考えればもしかして…。
彼らが成功したら、音楽産業がアルバムではなく曲を売らざるをえなくなったのと同じようなラジカルな変化が金融業界に訪れる。音楽業界が盛んに抵抗 したけど、無駄だったことを思いだそう。金融機関の利用も、罠や落とし穴なし、おかしな手数料なし、よく読めない小さな活字で印刷されている有害事項なし になるのだ。隠し立てをしない、消費者の金融音痴につけ込まない、従来のように必ず銀行が勝ってユーザが負けるゼロサムゲームでない、そんな金融業界を夢 見ようではないか。オープンソースやSaaSも、最初は眉唾で見られ、こてんぱんにけなされたが、今ではどこの会社でも当たり前のように使っている。
金融業界はあまりにも長らく、反イノベーション的で反消費者的だったのだから、革命的オンライン企業たちは最初から完璧を目指す必要はない。そして そこに、利益機会がある。たとえばすでにオンラインの金融サービスを2社も作って売った経験を持つCasaresによれば、デジタルの送金コストはかぎり なくゼロに近いのに、銀行は知らん顔をして高額な手数料を取っている。従来の電話会社の態度も同じだ。モバイルが価格破壊をやる前は、別の州にかける電話 はべらぼーに高かったのだ。
・・・
最近は急に、金融系のスタートアップが気になる存 在になったようだ。Webのビリオンダラー企業を作る第一歩は、良いチーム。第二歩は良い製品。第三歩は市場機会。そしてとくに重要な第四歩は、安易な金 の誘惑に対して“ノー”と言うことだ。シリコンバレーではだいたい10年に5社ぐらい、数十億ドル規模の公開企業が生まれている。2010年代には、その 中の少なくとも1社が金融企業になるだろう…やっと。
それは、「マイクロファイナンス」。資金貸与の際、複数の人に保障してもらうことで、無担保貸付を行うというものです。そのためには、ビジネスプランを複数の人に納得してもらう必要があります。
また、マイクロファイナンスは週1回~月1回、融資を受けた方と面談します。場合によっては集団面談を行います。これが、個人経営の人々を結束させ、孤独にせず、経営の失敗を早めに手を打つことで最貧国でも95%以上の返済率を確保しています。
日本の信用金庫・信用組合が似たような構造なのですが、もともとの「無尽・頼母氏」といった共同体金融が、今では経営者一族や大株主に支配される構造となり、結果的にどのように預金・資金を集め融資しているのかはっきりしなくなりました。
ですが、これからは発展途上国で成功しているマイクロファイナンスを、ITで結びつけて効率化できるような気がします。 というわけで
「銀行さん、頑張ってや!
今は融資先も大変やと思うけど、個別の商店の応援が難しいやんか。商店街の応援、実はアンタがやると一番効率よくできると思うんやで!」
ということであります。
消費者金融サービスに注力するのもいいけど、頑張ってる経営者の応援もよろしく!